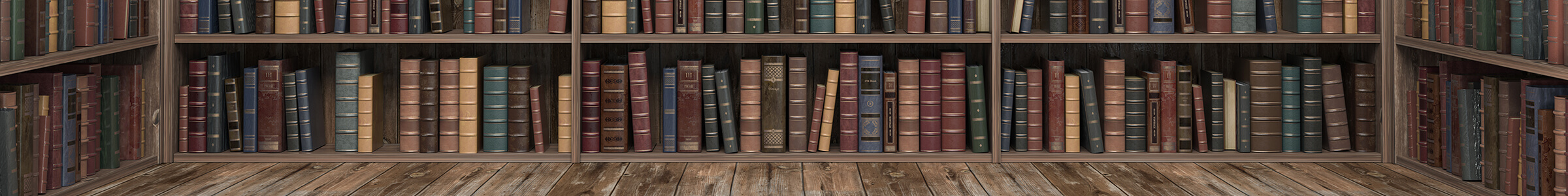現在、法政大学大学院連帯社会インスティテュート卒業生(労働組合プログラム)の修士論文を集めて一冊の本を編もうとしている最中である。論文作成を直接指導した学生は31名である。31名の修士論文の中から、私自身の関心に沿って産業別労働組合の機能、労働組合の政策参加、未組織労働者の組織化活動という3つのテーマに関連する論文9本を選んで、本を編もうとしている。本の仮のタイトルは『連帯社会と労働組合』。私は編者として9本の論文に目を通し、コメントを書き、修正が必要な場合は修正をお願いするという役割を担うことになっている。
ただ、集めるだけでは申し訳ないと思い、この3つのテーマに関するこれまでの研究を渉猟し、レビュー論文を書き、卒業生たちの論文をその中に位置付けようと考えた。レビュー論文のために、多くの著作を読まなければならないことになった。多くが既に読んだことのある著作なので、さほど困難ではないかと高をくくっていたのだが、そうでもなかった。内容を忘れているものも多いし、また読んでないものもある。
この小文は、そんな中で出遭った衝撃が書かせたものである。
レビューの対象は、先の3つのテーマの他に、労働組合の効果も含めている。このテーマで書かれた修士論文はないのだが、私自身は労働組合研究の出発点から組合効果について関心を抱いていた。2人の友人とともに刊行した『労働組合は本当に役に立っているのか』(総合労働研究所、1988年、共著者は佐藤博樹、神谷拓平)で、私は次のように書いた。「組織率が減りつづけることがなぜ問題なのだろう。労働組合はわたくしたちのくらしに本当に役立っているのだろうか。そしてこれからも役立つのだろうか」(p.9)。私自身は計量経済学の素養もなく高度な統計手法も使えず、組合効果を計量的に測定することはできていないが、組合効果への関心はいまだに持っている。組合効果に関する研究もレビューしているのは、これから連帯社会インスティテュートに入学してくる大学院生を含め、若い研究者に関心を持ってもらうためである。
その一環として都留康『労使関係のノンユニオン化』を読むこととなった。組合効果に関する実証研究部分からは学ぶことも多く、これまでの研究蓄積に少なくない貢献をしていると思う。だが、理論を論じた第1章は疑問符のつく点が数多く見られる。その最大のものが「4 小池のホワイトカラー化組合モデル」と名づけられた節である。都留は小池モデルを次のように解説する。
「第1に、発言がなされるのは内部労働市場(その核心は内部昇進制)が形成され、退出のコストが高くなるためである。第2に、内部化の特徴は、技能の企業特殊性度と技能の高さの積であり、その大きさに応じて浅い内部化と深い内部化とがある。第3に、日本では、深い内部化が一般的であり、深い内部化がホワイトカラーだけでなくブルーカラー労働者にも及んでいる・・・。第4に、そうしたホワイトカラー化の内実は、技能上関連の深い職場間での、OJTを通じた幅広い経験とそれを通じた生産の仕組みの理解である。第5に、深い内部化は退出コストを著しく高くする。このため解雇の可能性をめぐって発言の必要性が高まる。発言はパイの増大と分配をめぐってなされる。第6に、深い内部化のもとでの労働組合は、キャリアの後半(管理職)をカバーしないため、さしあたりは交渉力が弱いと考えられる。しかし、高い技能を要する職場では、個人の労働意欲が重要であって、これを左右しうる組合に対しては、企業としても発言を認めざるをえない。以上が小池の論理である」(p.18)。
さらにフリーマン=メドフと小池における発言の位置づけの相違という図1-2が示され、小池モデルとして、キャリアの企業特殊性に基づく内部化→離職率の低下→従業員による発言の必要性の増大→組合によるパイの増大に関する発言→生産性の上昇というルートが描かれる(p.19)。
この文章を読み図を見て私は驚愕した。私は小池和男「序説-ホワイトカラー化組合モデル-問題と方法」(日本労働協会『80年代の労使関係』日本労働協会、1983年、所収、pp.225-246)は、労働組合が企業別組合という組織形態をとる理由、また企業別組合が生産に協力し経営に発言する背景、企業別組合の交渉力の源を論じた仮説だと40年間思い続けてきた。したがって、都留の解釈、とりわけ図は、まったく理解できなかった。小池モデルに離職率の低下や生産性の上昇などという概念はあったのだろうか。職種別組合ではなく、企業別組合にもちゃんと存在理由があるのだと言っていたのではないか。こうした疑問が次々と湧いてきた。そこで知り合いに頼んで『80年代の労使関係』を借用してもらった(引退時に蔵書を大量に処分して手元にはない。他方、引退者には図書館の利用はなかなかに難しい)。
小池(1983)が批判の念頭に置いているのは「古典的教科書的組合観」つまり「横断組織こそ本来の労働組合だ、という考え方」(p.225)である。批判の出発点として内部労働市場を置く。内部労働市場とは「主に企業内で賃金がきまり、企業内で労働者が賃金の高い仕事へと移っていくことをいう。」「労働者の目的がより高い賃金をめざすものだとしよう。そうならば、内部労働市場のもとでは、昇進がきわめて大切になる。賃金のより高い仕事への移動である。内部昇進制だから、それは企業内の出来事であり、そのルール形成に発言する団体として、企業ごとの労働者組織が必要となる」(p.228)。
「また、退出コストが高い以上、解雇はまことに由々しい大事である。長く勤めたものにとって、他企業に移れば、また一から出直しになる。解雇につきぜひとも発言する労働者組織が必要である。解雇は企業ごとにおこる。企業別の組織が必須となる」(p.228)。
内部労働市場を前提とすると、昇進(あるいはキャリア)のルール、解雇について発言する労働者組織としては、企業ごとの組織が必要となる。こう解釈するのが普通であろう。私が先ほど指摘したように、労働組合が企業別に組織される理由である。なお、誤解を招かないよう、一点だけ付け加えておく必要がある。小池は、内部労働市場のもとでは必ず企業ごとの労働者組織、企業別組合が成立すると論じているわけではない。内部労働市場のもとで、昇進、キャリア、解雇に関して発言する団体としては、職種別組合ではなく、企業別組合がふさわしいと論じているのだと私は思う。
さらに、労働組合の行動にも変化が生じる。「企業の盛衰が労働者の雇用にひびく。企業がのびれば昇進が早くなる。逆におとろえれば、昇進が遅れ、甚だしきは解雇のおそれがある。競争企業に敗けないよう、企業の生産に協力するのは、内部労働市場のもとではむしろ自然の帰結である」(p.228)。
以上の説明は日本に限ったことではない。アメリカのローカルユニオン、ドイツのベトリーブスラートも事業所ごとの労働者組織である。以上の論理を「ほんの一歩すすめるだけで、こんどはいまの日本と他国の差を説明することになろう。その一歩とは、内部化のていどに深浅を区別するにすぎない」(p.229)。
「深い内部化とは、より上位の仕事まで企業内で昇進していくしくみをいう。あるいは企業内でより幅広く経験する場合もある。そのもつ技能はより多くの仕事をこなし高くなるからである」(p.230)。
深い内部化が先進諸国でどの程度見られるのか。これを年齢別の賃金プロファイルから推測する。すなわち「賃金が20歳代前半を100としたとき、後に150以上にまで上がり、しかも入職後20年近くも上がりつづける場合を、深い内部化とみよう」(p.231)。
ECの賃金統計と日本の賃金統計を比較した小池自身の別の研究を踏まえて、次のように述べる。「①深い内部化は日本だけではなく、欧米にもそのホワイトカラーに広く認められるが、②日本により厚くみられる。日本ではブルーカラーの一部をまきこんでいる。③とはいえ、日本でも深く内部化しているのは少数派にすぎない。要するに、日本のいまの特徴は、大企業ブルーカラーの『ホワイトカラー化』なのである」(p.231)。
小池が論じているわけではなく、私の解釈にすぎないのだが、企業別組合が工職混合組合であるという一つの特徴が維持されている理由の一つとして、大企業のホワイトカラーとブルーカラーが同じような性質をもっていることを挙げることができるのではないか。寄り道をしてしまった。小池モデルの解説に戻ろう。
ブルーカラーの「ホワイトカラー化」がみられる大企業の企業別組合の特徴は何か?
「まず退出コストはきわめて高くなる。若いうちはともかくあるていど勤続すれば、先の昇進の見通しも深く、熟練の企業特性は一層つよまるからである。他へ移るコストは甚だしく、発言の必要は格段に高まる。発言の対象がパイの増大におよぶ点は内部化一般の傾向である。それがとくにつよまる。自分のキャリアが企業内にビルトインされているだけに、企業の盛衰の自分の雇用におよぼす影響はまことにつよい。企業の経営に大いに発言せざるをえない」(p.233)。
内部労働市場の下での昇進や解雇に発言し、生産に協力する企業ごとの労働者組織の発言の必要性が「格段に高まる」、「大いに発言せざるを」えなくなる。質的というよりも程度の違いだと考えてよいように思う。事実、「ここまでは、さきに展開した内部化一般の論理と基本的にはちがわない。一歩おしすすめたにすぎない」(p.234)と論じている。だが、発言力、交渉力の源が危うくなる可能性が出てくる。
企業別組合は「組合員の職業的生涯をカバーしきれなくなる」「深い内部化とは、少なくとも一部の人が中下級管理職への見通しをもつ、ということである。そこへ進めばしばしば組合員でなくなる」(p.234)。「・・キャリアの後半に、組合からはなれる可能性があれば、組合にそのすべてを託すわけにはいかなくなる。しかも、管理職への昇進は激しい競争」(p.234)である。「こうした状況では、労働組合の、経営に対する交渉力は、格段におちる。当然、ストライキも打ちにくい。・・自分の企業のみで長いストライキを行なえば、競争企業におくれをとり、結局自分の雇用にひびく」(p.234)。
管理職をめざす少なくない組合員にとって、企業を危うくするような労働条件の引き上げやストライキは自らの首を絞めることになる。こう考えればよいだろうか。「総じて、以上のことは、労働組合を御用組合のようにみせる」(p.235)。
この欠点を埋めるのが深い内部化がもたらす高い技能である。「高い技能を要するところでは・・『個人の努力』の範囲が大きい。高い労働意欲か否かによる差異が甚だしい。労働組合と組合員がパイの増大への寄与を減らせば、その経営への打撃は大きい。これを経営側からいえば、高い労働意欲をひきだすには、それなりの発言を認めざるをえないことになる」(p.235)。
以上が私の理解した範囲での小池「ホワイトカラー化組合モデル」である。このモデルが、労働組合が企業別組合という組織形態をとる理由、また企業別組合が生産に協力し経営に発言する背景、交渉力の源を論じた仮説だという私の考えは的を外しているのだろうか。キャリアの企業特殊性に基づく内部化→離職率の低下→従業員による発言の必要性の増大→組合によるパイの増大に関する発言→生産性の上昇を論じたモデルであるという都留の解釈の方が、的を大いに外しているのではないか。「ホワイトカラー化組合モデル」を説明している第1節、第2節(pp.225-237)で、「離職率(の低下)」という単語は一度も出てこない。「生産に寄与する」「生産に協力する」という文章は出てくるが、「生産性」という単語はフリーマン=メドフ、ライベンシュタインの説を取り上げている文章で、彼らの言葉として出てくるだけである。
先行文献からモデルを学び、それを踏まえて自分なりのモデルを構築することは研究者にとって面白い作業であるし、それが成功すれば学界としても意義あることだと思う。私自身も小池「知的熟練論」に学び、知的熟練が発揮されるのは「製造現場の一般労働者が、・・生産管理業務の一部を実行している」(中村圭介『日本の職場と生産システム』東京大学出版会、1996年、p.10)時ではないかとの仮説を立てて調査研究を進めたことがある。この拙著について小池和男先生が丁寧な書評を書いてくださった(談話室の「研究業績展覧室」の「10.PDF」の1990年代に収めている)。私の「知的熟練論」理解を認めてくださったからだと自分では思っている。
著書や論文を読み、講義を聴く学生たち、受講生に常に「その人の思考の枠組みにそって、その人の主張を正しく、しっかりと理解することが大切です。自分の枠組みを前提につまみぐいのように理解することは良いことではありません」と説いている。東京大学でも、法政大学でも、Rengoアカデミーでもそう説いてきたし、今もそうである。
私はこれまで先輩、友人の著書の書評を書いてきた。川喜多喬『産業変動と労務管理』(日本労働研究機構、1989年)、井上雅雄『日本の労働者自主管理』(東京大学出版会、1991年)、水町勇一郎『労働社会の変容と再生』(有斐閣、2001年)『集団の再生』(有斐閣、2005年)などである。いずれも先の「研究業績展覧室」の「10.PDF」で閲覧できる。そして石田光男『仕事の社会科学』(ミネルヴァ書房、2003年)、石田他著・編『GMの経験』(中央経済社、2010年)『日本自動車企業の仕事・管理・労使関係』(中央経済社、2009年)『日本のリーン生産方式』(中央経済社、1997年)についても書評している。三爺の会のメンバーである石田さん(もう一人は猪木武徳さん)の著作については「石田光男を読み解く」「石田光男の焦燥と孤独」という書評論文を書いている(ネットで検索すればすぐにヒットする)。著者からはいずれも好意的な返事があり、しっかりと「理解できているな」と自分で満足している。石田さんからは「墓碑銘を描いてくださり、ありがとう」という言葉をいただいた。
アダム・スミスが私なりの『道徳感情論』をどう評価してくれるかは残念ながらわからないのだが。
私がこうした文章を書いたのは、都留さんに対する個人的な恨みからでは、もちろんない。著書や論文をしっかりと正しく読むことの大切さ、著者が何をどう考え、どう執筆したのかを著者の身になって理解することの大切さを主張するためである。「リサーチクエスチョン」(談話室の休憩室の「趣味」の部屋に記載)で示唆したのと同様の危惧、不安を抱いているからである。労働研究の今後はどうなってしまうのか。引退した、老齢の研究者の単なる杞憂であればよいのだが。
なお、私は都留さんのメールアドレスを知らないので、もし知っている方がおられましたら、お伝えください。反論は大歓迎です。